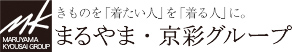着方レッスンコラム着方レッスンコラム
着物の左前とは?由来と合わせるコツを解説
2025.02.26

こんにちは! 「着たい人を、着る人に」 まるやま・京彩グループです。
ファッションではTPOを求められます。これは着物も例外ではありません。着物におけるTPOは、柄や着物の種類だけでなく着付けも関係します。そのなかでも有名なのが「左前」です。
とはいえ、左前の状態がいまいちピンとこない方や、なぜ失礼なのかが分からない方もいらっしゃるでしょう。そこで、左前の由来とそれを避けるためのテクニックをまとめました。着付け初心者の方は、ぜひご覧ください。
目次 [hide]
着物の正しい前合わせはどっち?

着物の前合わせは、右の襟が上に重なっている様に見える着方を「右前」といいます。着物はすべて右前が正しい前合わせです。着物を着る時は必ず自分から見て左の衿が上に来るように着付けましょう。
襦袢も必ず右前で着付ける
着物の下に着る襦袢も、着物と同じように右前で着用します。見えない部分だからといって、適当に着付けないよう注意しましょう。
襦袢は着物をきれいに見せるための土台であり、着付けの仕上がりを左右する重要な要素です。よりきれいに着物を着こなしたいなら、着物や帯だけでなく、襦袢の正しい着用方法もおさえておきましょう。
左前がよくない理由

「着物は必ず右前で着付ける」と聞くと「なぜ左前ではいけないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。実は左前は死装束、つまりご遺体に着せる時の着方なのです。そのため、左前で着物を着るのは縁起が悪い、マナー違反だといわれています。
普段はもちろん、はたちのつどいや結婚式などの場面で左前の状態で着付けると、非常識な人として扱われてしまいます。お祝いの席などに着物を着ていく際は、着付ける前はもちろん、そのあともきちんと右前になっているかを確認しましょう。
左前が死装束となった由来
左前が死者の服装となった理由は諸説あります。
- 死者の世界は生者の世界と反対になっているという考え
- 三途の川で死者の服をはぎ取り、その重さで罪を測る「奪衣婆」と呼ばれる精霊を避けるためのおまじない
- 死者を神仏に近い存在とみなす考え
こうした考えが複数あり、左前は縁起が悪い着方であるという考えが一般的になりました。由来を知らない方でも左前が死者に着せる着付けだと知っている方はたくさんいます。着物を着る時は、左前にならないよう注意しましょう。
衿合わせをそろえるコツ

相手から見て「y」の形にする
右前は相対した人から見て衿の部分が小文字の「y」の状態になります。鏡などで確認するときは、衿の形が「y」の字になっているかを確認しましょう。
なお、スマートフォンで写真を撮って確認する方法もありますが、この時は反転機能がオフになっているか確認してから撮影してください。反転機能がオンになっている状態だと、間違った状態が反転されて左前として表示されてしまいます。撮影する際は注意しましょう。
右手が懐に入るか確認する
着物をはじめとした衣類は、右利きの方が懐に手を入れやすいように作られています。着物を着た時、右前になっているなら右手が懐に入るはずです。入らない場合は左前に着付けてしまっているため、やり直しましょう。
また、着付けの時は右手が懐に入ることを意識して着付けることで、間違いを予防できます。衿の形と合わせて覚えておきましょう。
着物の柄も衿の見分けポイント
着物は柄や刺繍が帯や合わせで隠れないように配置されています。肩や衿周りの場合、左側の方に柄や刺繍が多いはずです。どちらが前か迷った時は、着物の柄を確認して華やかに見える方を外側に持っていきましょう。
まとめ
着物の左前は、着ていく場所を問わず非常識だとみなされる着付け方です。初めて着物を自分で着付ける方や、着物を着始めた方がよくやる間違いでもあります。着物を着る時は左前を避ける着方はもちろん、着たあとに鏡やスマートフォンで確認する習慣を身に付けましょう。
まるやま・京彩グループでは、着物好きの皆さんがステキな着物ライフを送れるよう、お役立ち情報を発信していきます。
着物の選び方や着こなしについて、もっと詳しく知りたい方は、ぜひまるやま・京彩グループの着付け教室、無料体験レッスンにお越しください。
経験豊富なスタッフが、あなたにぴったりの着物選びをお手伝いします。